導入事例

「無関心」を越えて、“当たり前”をつくる——中川悠が語る大阪・関西万博カームダウンルーム「1坪のハグ」に込めた思い
阪神・淡路大震災で見た光景が、「社会の無関心」に向き合う原点になった——そう語るのは、NPO法人チュラキューブ代表理事であり、大阪国際工科専門職大学准教授の中川悠さん。障がいのある方々の就労支援や地域食堂の運営など、多様な人々が安心して暮らせる社会づくりに挑んできた中川さんは、株式会社Yogibo(以下Yogibo)が提供した2025年大阪・関西万博のカームダウン・クールダウンルーム「1坪のハグ」の開発にも検討委員として参加しました。「特別な配慮」ではなく「当たり前の選択肢」としての空間を目指し、専門分野を越えて交わされた議論と、そこに込めた想いを聞きました。
検討委員・ファシリテーター:中川悠(NPO法人チュラキューブ 代表理事/大阪国際工科専門職大学 工科学部 准教授)
聞き手(主催者):大森 一弘/株式会社Yogibo 執行役員
社会問題への関心の原点、阪神・淡路大震災の記憶
大森:
中川さんはNPOの代表や大学の先生など、いろいろな顔をお持ちですが、まずは、これまでどんな活動をされてきたのか教えていただけますか?
中川さん:
僕は29歳の頃から今まで、障がいのある方々と関わる活動を続けてきています。最初にはじめたのは、障がいのある人たちが働く訓練をする施設に関わって、「誰かの役に立つこと」「収入を高めること」を実現するためのプロジェクトづくりでした。その後、京都市役所とともに、伝統工芸の後継者がいない問題と、障害のある方の働く場所が少ないという問題を、結びつける「伝福連携」というとりくみにも携わり、今は企業に採用された障がいのある方々が心理的な安全を保ちながら働き続けることができるようにと、企業と一緒に「障がいのあるスタッフが地域に暮らす皆さんのために料理を提供する」、こども食堂やシニア食堂を立ち上げ、運営をするプロジェクトも進めています。
また、2024年から大学の准教授として「地域課題✕テクノロジー」について教える仕事もしていますが、これまでの活動を通してずっと感じてきたことがあるのです。それは、社会にあるいろんな問題の根っこには「無関心」があるんじゃないか、ということなんですよね。
僕自身がこの「無関心」という問題に真剣に向き合うようになったのは、高校2年生の時に経験した阪神・淡路大震災がきっかけでした。当時、僕は山梨県の全寮制の高校にいて、実家は兵庫県の伊丹市にありました。大震災が起こった日、山梨県の寮のテレビで見た、神戸の街が燃えている光景は今でも忘れられません。その後すぐに兵庫県西宮市の教会の住み込みボランティアに駆けつけ、2週間だけ、被災者になった方々と一緒に過ごさせていただいたんです。家や家族を失う人がいるという現実を目の当たりにして、「当たり前の日常って、こんなに簡単になくなってしまうんだ」と痛感しました。この経験が、僕が社会問題に関心を持つようになった原点になっています。
「自分ごと」として考えるには?カギは「体を動かす想像力」
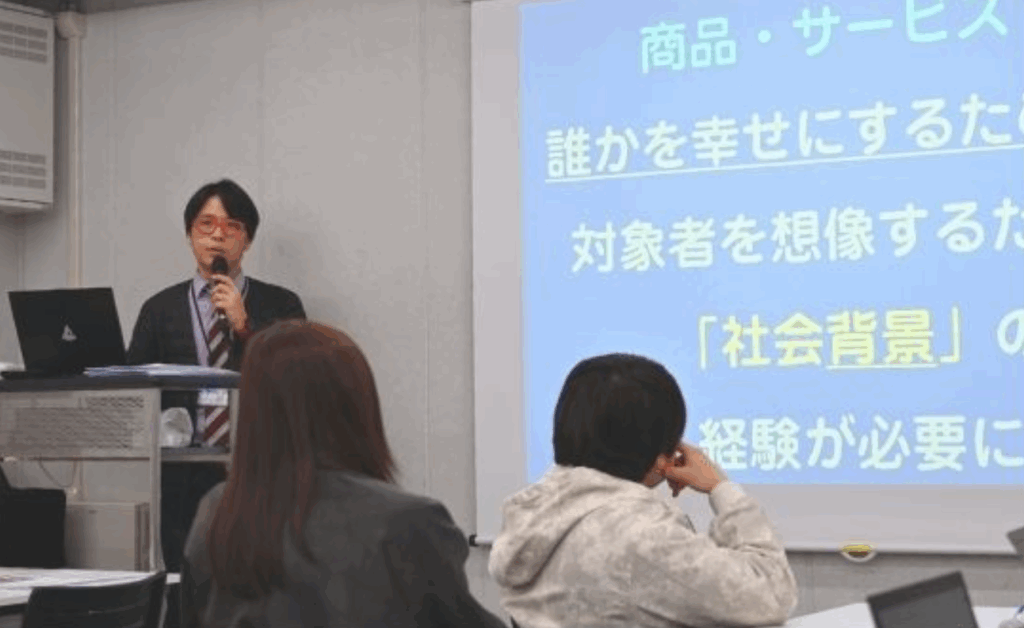
大森:
震災というご自身の体験が、社会の問題を「自分ごと」として捉えることにつながったんですね。
中川さん:
そうですね。ただ、多くの人にとって、自分が直接経験していないことを「自分ごと」として捉えるのは、やっぱり難しい。例えば、先ほどお話ししたこども食堂も、本当に困っている子がいると頭では分かっていても、どこか他人事になってしまいがちになってしまいますよね。
じゃあ、どうすればその距離を縮められるのか。僕は、そこに「想像するだけじゃなくて、体を動かして現場を体験する」というアクションが必要不可欠だと考えています。
先日、小学3年生の娘と、昔の地図を片手に近所を歩いてみる、ということをしました。最初はただ僕の後ろをついて歩いてぼんやりと町を歩いていた娘に、「2周目はあなたが案内するんだよ」と地図を渡してみたんです。すると、娘の目が真剣になり、周りの景色や看板をよく見て、地図を見ながら方向を考え始めたんです。これは面白い発見でした。
情報として知っているだけじゃなくて、実際に自分で体を動かして、五感で体感することで、目の前のぼんやりしている情報が、初めて「自分ごと」になる。この「ただ単にネットやニュースを見て考える想像力ではなく、リアルな体験から生まれる想像力」こそが、社会問題への無関心を乗り越えるカギになるんじゃないかと思っています。
「特別な配慮」から「当たり前の選択肢」へ。万博が社会を変えるチャンス

大森:
その考え方は、今回開発されたカームダウンルーム「1坪のハグ」にもつながってきそうですね。
中川さん:
まさしくその通りですね。今回の万博というイベントは、普段は出会わないような世界中の国を知ったり、見たことがない素晴らしすぎるパビリオンや展示を見たり、世界中から集まる人に出会える絶好の機会です。そこでの初めての体験として「1坪のハグ」のような空間を目の当たりにしてもらうことは、すごく大きな意味があると思っています。
ただ大事なのは、これを「感覚が過敏な人など、特別な配慮がいる人のための場所」で終わらせてはいけない、ということです。なぜなら、僕らが目指しているのは、こうした空間が「当たり前の選択肢」として社会にあることなのですから。そのために、万博というたくさんの人が集まる場所で、多様なニーズに応える空間が「標準装備」として示されることには、社会の「当たり前」を変えていける、すごく大きな可能性があると思っています。
いろんな分野の専門家が集まると、何が生まれるか
大森:
今回のプロジェクトには、様々な分野の専門家が検討委員として参加されました。このように、多様なメンバーで協力していくことについては、どうお考えですか?
中川さん:
専門分野の垣根を越えて学び合うことを「越境学習」と言ったりしますが、今回はまさに毎回が「越境」の連続でした。建築、福祉、そして実際に困っている当事者の視点など、それぞれの専門家が自分の知識を持ち寄って話し合う中で、僕自身も本当に多くのことを学ぶことができましたね。例えば、カームダウンルームの部屋に「鍵をかける」かどうか、「利用時間をどう設定するか」。また、どこまでが介護者でどこからが当事者なのか、といった、1つの空間をハードとして作るだけではなく、ユーザーはどんな状況にある人なのかをできるかぎりたくさん想像し、話し合っていくんですよね。僕一人では考えつかなかったような具体的な問題点について、深く考えることができました。
それぞれの専門性を尊重しながらも、そこから一歩踏み出して、お互いの領域を越えながら学び合う。そうした越境しながら学びを深めていくプロセスがあったからこそ、「1坪のハグ」は多くの当事者の方から「現場のことをよく分かっているね」と共感してもらえたんだと思います。
これからの社会に必要なこと
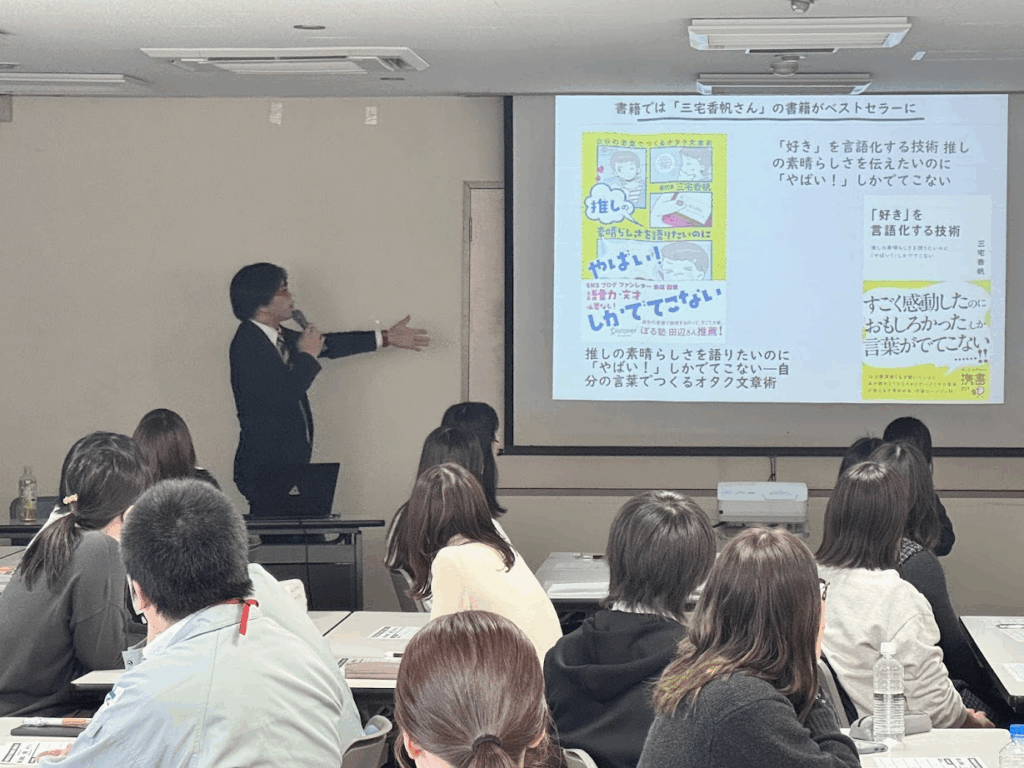
大森:
最後に、今回の取り組みが、今後どのように社会に広がっていくことを期待されますか?
中川さん:
一人ひとりの意識が変わるのを待つだけじゃなくて、社会の「仕組み」そのものを変えていく必要があると感じています。今の社会は、「みんな同じであること」を前提に作られすぎている気がします。そうではなくて、人間はそもそも多様だということを前提にした仕組みを、社会のいろんな場所に作っていくこと。そのための具体的な「答え」を示していくことが、これからの僕たちの役割だと考えています。
今回の「1坪のハグ」は、そのための大きな一歩です。この取り組みが、一人ひとりが自分にとっての「心地よさ」って何だろうと見つめ直し、多様な人々が一緒に生きていける社会を思い描くきっかけになってくれたら、と心から願っています。
参考サイト:NPO法人チュラキューブ