導入事例
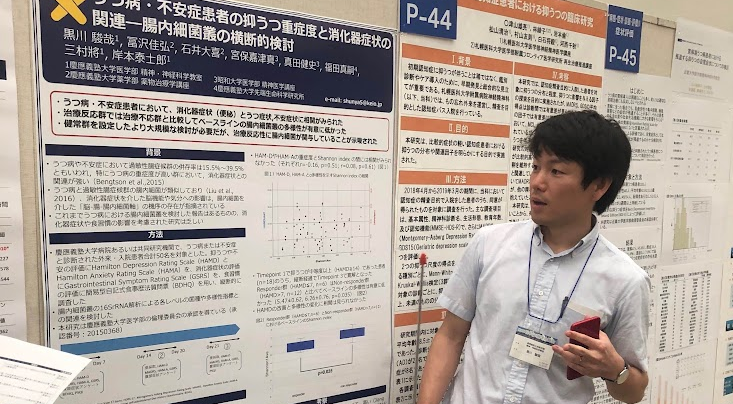
「一人ひとりが過ごしやすい社会」のために──精神科医・黒川駿哉さんが語る、万博カームダウン・クールダウンルームと“標準装備”としての多様性
2025年大阪・関西万博の会場内に設置された「カームダウン・クールダウンルーム」。そのうちの一つ「1坪のハグ」は、感覚過敏や不安を感じやすい人が安心して過ごせる空間として、Yogiboを中心に設計された休息の場です。
この空間づくりに、医学・産業・研究の三つの視点から深く関わったのが、精神科医の黒川駿哉さん。自らの原体験からはじまり、福岡での子どもの居場所づくり、そして万博での実践へ──多様な立場の人々と共に考えたプロセスを通じて、「インクルーシブな社会づくり」に必要なこととは何かを語っていただきました。
検討委員:黒川 駿哉(医学博士 精神科医 / 慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター 特任助教 / 子どものこころ専門医)
聞き手:中川(NPO法人チュラキューブ 代表理事/大阪国際工科専門職大学 工科学部 准教授)
精神科医、産業医、そして研究者。三つの顔を持つ理由
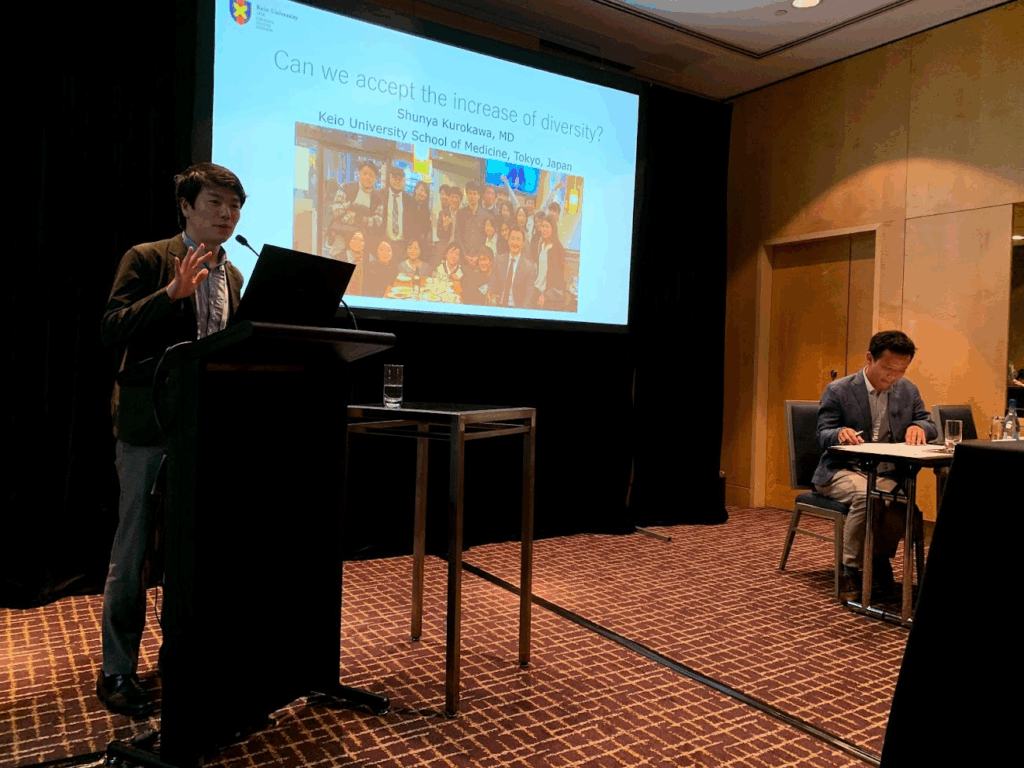
中川:
黒川先生は、精神科医として臨床に立たれる傍ら、産業医や大学での研究など、非常に多岐にわたる活動をされています。まずは、先生ご自身の活動の原点や、現在の働き方に至った経緯についてお聞かせいただけますでしょうか。
黒川:
精神科医になったのは、自分自身が思春期に不安定な時期を過ごし、その時に多くの人に助けられた経験が大きいですね。「この人に出会えて良かった」と思える大人がいたからこそ、今の自分がある。だから、自分もいつか、誰かを支えられるような存在になりたいと思ったのが原点です。
現在は臨床医、産業医、そして大学での研究という3つの軸で活動しています。もともとは臨床が中心でしたが、いわゆる「5分診療」の限界を感じることが多くありました。一人の患者さんとお話をする時間は、基本的にたった5分。その中で症状を聞き、診立てを修正したり治療方針などの判断までしていくんです。でも、本音を言うと患者さん一人ひとりとじっくり向き合う時間も大切にしたい、でも保険診療の枠組みでは難しい。そうしたジレンマの中で、もっと違う形で社会に貢献できることがあるのではないかと考え、NPOのお手伝いや、福岡で子どもたちのための居場所づくりを始めました。今はフリーランスに近い形で、それぞれの活動にバランスよく時間を使いながら、自分にできることを模索している、という感じですね。臨床だけでは見えない社会の課題に、産業医として企業の視点から、研究者としてアカデミックな視点からアプローチすることで、より多角的に物事を捉えられるようになったと感じています。
「安心できる居場所」から始まった、空間づくりの探求
中川:
福岡で子どもたちのための居場所を作られたことが、今回、万博のカームダウンルームに関わる大きなきっかけになったと伺いました。
黒川:
そうですね。福岡で、特に不登校の子どもたちが学校や家庭以外の「次のステップ」として安心して過ごせる居場所を作りたいと考えたんです。エネルギーが回復してきた子たちが、社会と再び繋がるための、心理的負荷の少ない場所が決定的に足りないと感じていました。その時に、感覚過敏に配慮した「センサリールーム」のような空間が必要だと感じ、株式会社Yogibo(ヨギボー)さんに問い合わせたのが、大森さんとの出会いのきっかけです。当時は、療育センターなどで「カームダウン・スペース」や「スヌーズレン」といった空間の重要性を学んでいましたし、実際にそうした空間に助けられているという当事者の声も聞いていましたから。
中川:
居場所では、具体的にどのような空間をイメージされていたのですか?
黒川:
「ごきげん部屋」と「見守る部屋」という二つのコンセプトを考えました。一つは、周りに合わせることなく、一人で静かに過ごせる空間。もう一つは、人と関わりたい子が安心して過ごせる空間です。人疲れしやすい自分自身の経験からも、ただ「集まる場所」があるだけではなく、一人ひとりが自分の状態に合わせて過ごし方を選べる環境が必要だと考えました。その思いをYogiboさんの問い合わせフォームからお伝えしたところ、今回の万博プロジェクトにお声がけいただくという、予想もしていなかった展開に繋がりました。
多様な専門家との議論から生まれた、新たな視点

株式会社Yogibo提供のカームダウン・クールダウンルーム
中川:
今回のプロジェクトでは、感覚過敏の当事者である加藤さんや、建築・デザインの専門家、そして先生のような医療の専門家など、様々な分野の方々が集まって議論を重ねました。その中で、特に印象に残っていることや、学びになったことはありますか?
黒川:
非常に刺激的で、多くの学びがありました。特に印象的だったのは、それぞれの専門分野で使われる「言葉」の定義や捉え方が少しずつ違う、ということです。
例えば、私が医学的な意味合いで使っていた「運動」という言葉が、保護者の方からすると「スポーツ」のような身体を大きく動かすことだけを指しているように聞こえる、というご指摘がありました。私の中では、歯磨きや箸の上げ下げといった日常動作も「運動」に含まれていたのですが、その認識のズレにハッとさせられました。こうした小さなズレを、対話を通じて一つひとつすり合わせていくプロセスそのものが、非常に貴重な経験でしたね。
また、当事者の方が入ってくださったことも非常に大きかったです。良かれと思って準備していたことが、当事者の方からすると「そうじゃない」ということもある。例えば、視覚障がいのある方は必ずしも点字が読めるわけではない、むしろ音声読み上げ機能の方が馴染み深い方も多い、というお話もその一つです。多様な視点が交わることで、よりインクルーシブな空間デザインに繋がったと感じています。
万博が社会に示す「多様性という標準装備」
中川:
大阪・関西万博という大きな舞台でカームダウンルームが設置されることについて、どのような期待をお持ちですか?
黒川:
万博という社会的に影響力の大きいイベントで、こういった空間が「標準装備」として設置されること自体が、非常に強いメッセージになると思っています。「人間は多様である」ということを、言葉だけでなく「仕組み」として社会に提示することができるからです。
これまで、こうした配慮は「特別な誰か」のためのものと捉えられがちでしたが、そうではありません。誰もが、その時々の自分の状態に合わせて、過ごしやすい環境を選べる権利があります。今回の取り組みが、そうした認識を社会全体に広める大きなきっかけになることを期待しています。
中川:
万博が終わった後、この取り組みがどのように繋がっていくと良いとお考えですか?
黒川:
これが一つのスタンダードになって、万博だけでなく、駅や空港、商業施設といった公共空間や、様々なイベントで当たり前のようにセンサリールームやカームダウンルームが設置される社会になってほしいですね。そのためには、今回の知見を基にした客観的な「ガイドライン」の作成が不可欠だと考えています。どういった環境で、どのような目的で設置するのか、その際のルール作りなど、見よう見まねではなく、しっかりとした指針を示すことで、質の高い空間が全国に広がっていくはずです。
「仕組み」を変えることで、「意識」は変わる

株式会社Yogibo提供のカームダウン・クールダウンルーム
中川:
最後に、先生ご自身の今後の活動の展望についてお聞かせください。
黒川:
来年、発達性協調運動障害(DCD)、いわゆる「不器用さ」をテーマにした学会の大会長を務めさせていただくことになりました。この学会でも、医学の専門家だけでなく、教育関係者、スポーツ指導者、そして当事者やそのご家族など、様々な立場の方に参加していただき、今回の万博での経験を活かした場づくりをしたいと考えています。
かつて私は、個人の「意識」を変えることが先で、その結果として「仕組み」が変わっていくのだと思っていました。しかし、今は逆だと感じています。インクルーシブな「仕組み」を先に社会に実装することで、人々の「意識」は自然と変わっていく。今回のカームダウンルームは、まさにその好例になるのではないでしょうか。この流れを、さらに広げていくお手伝いができればと思っています。
中川:
本日は、医学的な知見から社会全体の仕組みづくりまで、非常に示唆に富むお話をありがとうございました。先生の今後のご活躍を心から応援しております。
